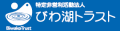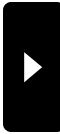地球温暖化とびわ湖
地球温暖化の波は、びわ湖に刻々と押し寄せています。下図からわかるように、
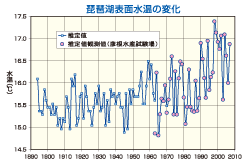 ファイル 7-3.gif
ファイル 7-3.gif
1950年以前には、びわ湖の表面水温は15.5℃前後でしたが、
2000年以降では16.5℃以上になっています。このような水温の上昇は、
湖の上下混合に大きな影響を与えます。
2007年1月から3月にかけて、びわ湖は例年にない暖冬を迎えました。
このことによって、湖は完全には混合しなかったようです。
なぜなら、湖底で計測した溶存酸素濃度の連続記録から、あきらかに過去とは
異なる傾向を見ることができるからです。特に、河川や湖岸から流入する酸素の
多い冷たい水は、ほとんど湖底まで到達しませんでした。
さらに、8月から9月にかけての猛暑が、追い討ちをかけ、水深90mより
深い水域において急激な酸素低下が観測されました。
10月から12月の約2か月にかけて、深い湖底の溶存酸素濃度は、
1.0mg/L以下という低い値を記録したのです。
自律型潜水ロボット「淡探」は、12月に今津沖の湖底観測を行い、
大量のイサザやヨコエビの死骸を発見しました(写真)。
 ファイル 7-1.jpg
ファイル 7-1.jpg
 ファイル 7-2.jpg
ファイル 7-2.jpg
この時期のイサザの大量死は、これまでに見られなかった現象であり、長期間、
低酸素状態にさらされた結果の酸欠死であると推定されます。
幸いに、2008年の1月から2月にかけて、寒い気候が続いたので、湖底の
溶存酸素濃度は十分に回復しました。しかし、3月に入り、気候が急に上昇し、
水温躍層が形成され、早くも湖底では酸素消費が始まりました。
一度酸素がなくなった湖底は、無酸素化しやすい傾向があるので、注意
しなければなりません。
地球温暖化は、今後さらに加速される可能性があります。高精度な監視と、
環境適合への備えが必要です。
地球温暖化の波は、びわ湖に刻々と押し寄せています。下図からわかるように、
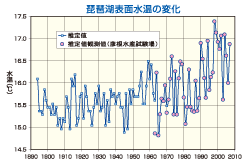 ファイル 7-3.gif
ファイル 7-3.gif1950年以前には、びわ湖の表面水温は15.5℃前後でしたが、
2000年以降では16.5℃以上になっています。このような水温の上昇は、
湖の上下混合に大きな影響を与えます。
2007年1月から3月にかけて、びわ湖は例年にない暖冬を迎えました。
このことによって、湖は完全には混合しなかったようです。
なぜなら、湖底で計測した溶存酸素濃度の連続記録から、あきらかに過去とは
異なる傾向を見ることができるからです。特に、河川や湖岸から流入する酸素の
多い冷たい水は、ほとんど湖底まで到達しませんでした。
さらに、8月から9月にかけての猛暑が、追い討ちをかけ、水深90mより
深い水域において急激な酸素低下が観測されました。
10月から12月の約2か月にかけて、深い湖底の溶存酸素濃度は、
1.0mg/L以下という低い値を記録したのです。
自律型潜水ロボット「淡探」は、12月に今津沖の湖底観測を行い、
大量のイサザやヨコエビの死骸を発見しました(写真)。
 ファイル 7-1.jpg
ファイル 7-1.jpg ファイル 7-2.jpg
ファイル 7-2.jpgこの時期のイサザの大量死は、これまでに見られなかった現象であり、長期間、
低酸素状態にさらされた結果の酸欠死であると推定されます。
幸いに、2008年の1月から2月にかけて、寒い気候が続いたので、湖底の
溶存酸素濃度は十分に回復しました。しかし、3月に入り、気候が急に上昇し、
水温躍層が形成され、早くも湖底では酸素消費が始まりました。
一度酸素がなくなった湖底は、無酸素化しやすい傾向があるので、注意
しなければなりません。
地球温暖化は、今後さらに加速される可能性があります。高精度な監視と、
環境適合への備えが必要です。